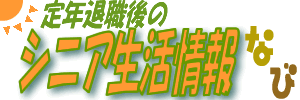
定年退職後に老後の人生を楽しむため、シニア世代の相続に関する情報を紹介。

カスタム検索
|
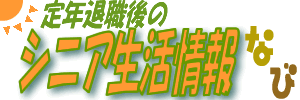 |
定年退職後に老後の人生を楽しむため、シニア世代の相続に関する情報を紹介。 |
||
|---|---|---|---|
|
|||
| | はじめに | お問い合せ | | |||
| ホーム | お金 | 資産運用 | 副業 | 住まい | 健康 | 働く | 学ぶ | 楽しむ | 介護 | 家族 | 暮らし |
|
相続家族に残してあげる資産を考えたとき、ふと頭に浮かぶのが相続問題です。 誰もが避けることのできない相続、相続対策はいつ始めても早すぎることはありません。 とくに相続税対策は、早ければ早いほど多くの財産をスムーズに相続人に承継させることが可能となりますので、今からその時に備えて準備しておくことが重要です。 1通の遺言書があれば相続人同士で争いが起きることを防ぐことができますし、相続税の節税対策をしていれば無事に相続税を納付できることと思います。 ●相続税のかかる人相続税は一定の金額を超える財産を残して亡くなった場合にかかる税金です。基礎控除額を超える場合には、相続税が掛かります。
例えば、法定相続人が妻と子ども2人の場合は「5,000万円+1,000万円×3人」=8,000万円までなら相続税はかかりません。 実際に相続税が課税される方は100人のうち約5人。 けっこう財産をもっているようでも、相続税のかかる人は意外に少ないのです。 100人のうち95人は相続税が掛からず、心配はありません。 おおまかに計算してみるだけで、相続税がかかるかかからないか、およその判断ができます。 ●自分の財産を把握現金や預金、株券、土地、建物、生命保険金や退職金など、ほとんどの財産が相続財産にあてはまります。相続対策は、自分の財産がどれだけあるか調査することがスタートラインです。 財産の分配についても、それぞれの評価を知った上で分配しないと、後々トラブルの元にもなりかねません。まず、自分の財産を整理してまとめてみましょう。
不動産については、所在地や面積、使用状況などによって財産の評価が違ってきます。 お墓、仏壇、祭具、生命保険金・退職金の一定額以下を受け取る場合などは、非課税財産となり、相続税はかかりません。 また、相続税を計算する上で、借入金などの債務・未払い税金・お通夜及び火葬費用などは、控除できます。 自分の財産がどのように相続されるのか法律の仕組みを知っておくことをお勧めします。 ●相続に対する対策相続に対する対策はついて、大まかに分けると3つの対策に分けることができます。1.遺産分割対策(紛争対策)
2.相続税の節税対策
3.納税資金対策
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| This site is written by Japanese. / Copyright © 2006 Katsudon right reserved. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||