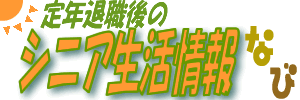
定年退職後に国民健康保険の退職者医療制度の被保険者となる場合に関する情報を紹介。

カスタム検索
|
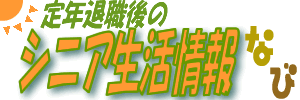 |
定年退職後に国民健康保険の退職者医療制度の被保険者となる場合に関する情報を紹介。 |
||
|---|---|---|---|
|
|||
| | はじめに | お問い合せ | | |||
| ホーム | お金 | 資産運用 | 副業 | 住まい | 健康 | 働く | 学ぶ | 楽しむ | 介護 | 家族 | 暮らし |
国民健康保険の退職者医療制度の被保険者となる場合長い間、会社や役所などに勤めて退職して人で、厚生年金や共済年金の支給を受けている場合は、65歳になるまでの間、一般の被保険者とは別の退職医療制度の適用を受けることになっています。 ●国民健康保険の退職者医療制度とは医療の必要性が高まる退職後に、退職者が会社等の健康保険から国民健康保険に移ることにより、国民健康保険の医療費負担は増大します。このような医療保険制度間の格差を是正するために退職者医療制度では、本人の自己負担と保険税のほか、職場の健康保険など出し合う拠出金でまかなわれます。 退職者医療制度は、長い間、会社や役所などに勤めて退職して人で、厚生年金や共済年金等の受給者とその扶養家族の方は、高齢者医療制度になる65歳まで退職者医療制度が適用されます。 出産・死亡などの給付は市区町村によってまちまちですが、国民健康保険の退職者医療制度には健康保険の傷病手当金や出産手当金に相当するものはありません。 医療機関で支払う自己負担額は、本人・家族とも外来・入院を問わず一般被保険者と同じ3割負担です。(義務教育就学前の乳幼児は外来・入院とも2割) ●退職者医療制度の廃止について退職者医療制度は平成20年4月より新たな高齢者医療制度(前期高齢者医療制度と後期高齢者医療制度)へ改定となり、段階的に廃止となります。ただし、平成26年度までの間における65歳未満の退職被保険者等が65歳になるまで存続されますので申請が必要になります。 ●退職者医療制度の加入条件退職被保険者(本人) 国民健康保険の退職被保険者となるためには以下の条件を満たした方のみが対象になります。
被扶養者(扶養家族) 上記の退職被保険者の家族が次の条件を全て満たす場合、届出により退職被保険者の被扶養者となります。
65歳から74歳までの人は「前期高齢者医療制度」、満75歳になると「後期高齢者医療制度」に切り替わります。 退職者本人に、退職者医療制度が適用されなくなったときは、被扶養者も同時に適用されなくなります。 ●退職者医療制度の手続き方法退職者医療制度の加入資格は、年金受給権が発生した日から適用になります。年金の受給権が発生し、年金をもらう手続きをすると年金証書が送られてきますので、14日以内に住所地の市区町村の窓口へ届け出をしてください。 一般の国民健康保険の保険証ではなく、「国民健康保険退職被保険者証」が交付されます。
●退職者医療制度の保険料保険料は前年度の所得を元に算出され、計算式は市町村によって異なります。保険料には上限がありますが、各市町村によよって保険料の上限も異なります。 ほとんどの市区町村は、所得割、資産割、被保険者均等割、世帯別平割の4つを組み合わせた額で保険料の額を決めています。 健康保険組合などは扶養する家族が何人いても、本人分の保険料だけで扶養家族も保険適用されます。 しかしながら国民健康保険の退職者医療制度には被扶養者の概念がないため、家族もいっしょに加入する場合は、その扶養家族分の保険料も必要になります。 定年退職者は前年度の所得が多いので上限近くになる場合もありますので、退職前に保険料額を算出して貰いましょう。
|
|||||||||||||||||||||||||||
| This site is written by Japanese. / Copyright © 2006 Katsudon right reserved. | |||||||||||||||||||||||||||